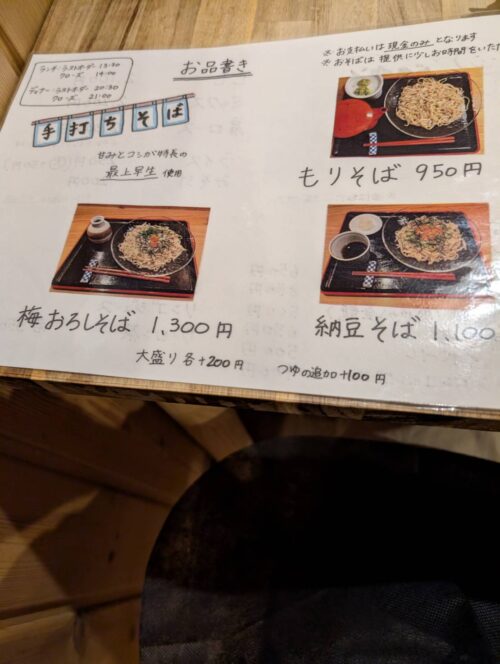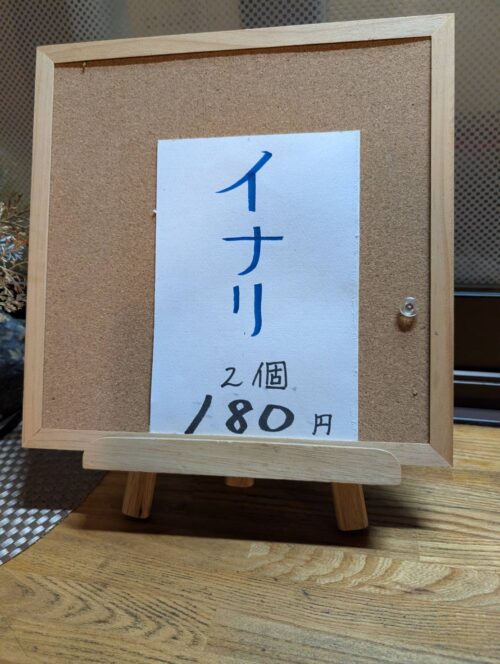近況報告
昨日は研究室研修がお休みで、QBを使ってCBTの対策をしていました。昨日やったのは呼吸器、腎泌尿器、循環器、血液、消化管、肝胆膵です。合計で350問をちょっと超えたくらいだったと思います。QBの問題は合計したら4000問くらいだったはずです。来週から授業が始まりますが、来月の半ばくらいには一通り目を通したいと思います。
図を書いて位置関係を把握しましょう
空間ベクトルだろうと平面ベクトルだろうと、面積や体積を求める問題が多かった記憶があります。問題文には何処にどんな点があるといった事が書かれています。これをしっかりと読み取って位置関係を把握して図に書きましょう。間違ってしまうと、問題を解く上で支障をきたします。逆に言えば、条件を読んで計算などをしている時に何かを間違えていたというサインにもなります。このようなミスにきちんと気づくためにも図はしっかりと書くべきだと思います。
解答する上で必要になるかどうかは分からなくても、得ることの出来る情報は取り敢えずは解答用紙に書きましょう。それで部分点が貰える可能性もあります。山形大学のベクトルの問題であれば(5)か(4)の前まのきちんと出来る部分はでは部分点ではなくてきちんと全部取らないといけない面はありますけど、札幌医科大学や旭川医科大学みたいに難しい問題が出る場合は部分点狙いという事も必要になります。
高校や予備校の先生は「取れるところをしっかり取れば合格出来る(共通テストでちゃんと取っているという条件ではありますけど)」と言いますが、図を書いたりしないと「取れるところをしっかり取る」ということのきっかけもつかめないと思います。
高1高2の場合は今の段階では基本をしっかりと理解して答えを導くべきで最初から部分点狙いといった事はあまりするべきではありませんが、図などをしっかり書くことは今のうちに心がけておきましょう。
追記
そろそろ受験校を絞る時期です。再受験に寛容な大学なども把握しないといけません。私が面接で地雷を踏んだ例です。なかなかお目にかかれないと思います。是非ともご購入してください。
![]()