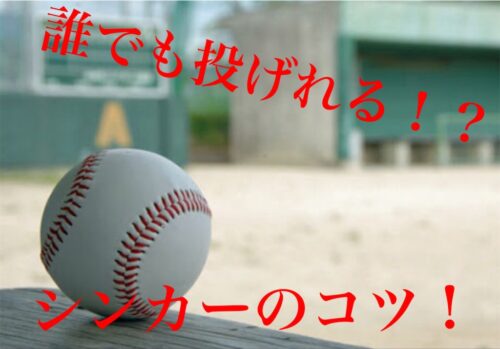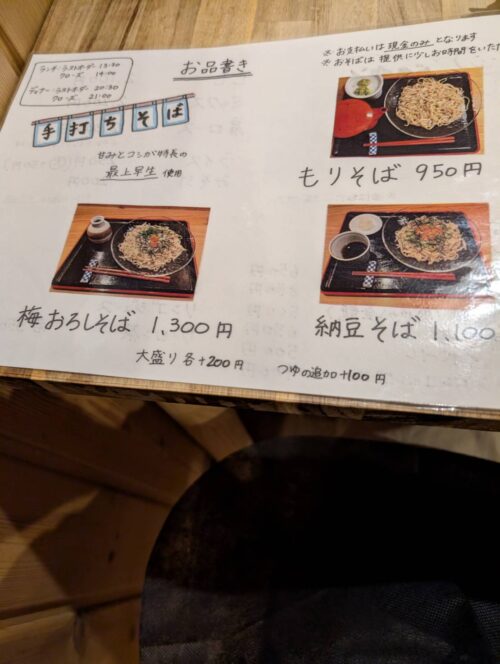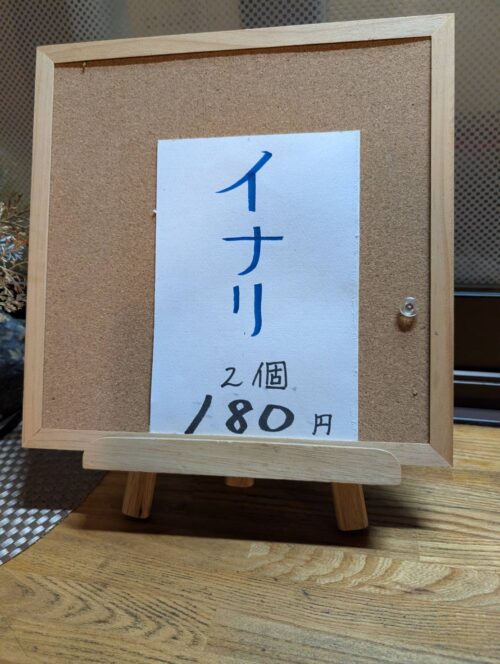最初は基礎からです
身内の諸事情により、ここ数日ブログを書くことが出来ませんでした。申し訳ありません。
四月から高校三年生になって受験生生活が始まります。それぞれに行きたい大学があると思います。それぞれの大学にそれぞれ特有の問題があります。しかし、その大学を志望するからと言っていきなりその大学の頻出分野といった風に勉強してはいけません。
まずは各科目の基礎をやってください。その基礎が無いと大学別の問題の対策も何もありません。例え、過去問をやって覚えたとしても「その問題だけ出来るけど、ちょっと変えられたら途端に全然できなくなる」という状況になります。それでは意味がありません。当然ですけど、傾向が変わったからと言って誰も大学側に文句を言うことが出来ません。解答に対して後日「ここは違うんじゃないか」と指摘をすることは出来ますが。仮に傾向変わったことに対して落ちた人たちが文句を言うことが出来てやり直しをしてもらったところで合格できる可能性は低いと思います。
この場合は合格した人たちは傾向を変えられても対応して合格点を取れた人たちということになります。つまり、傾向変えられても対応できる基礎力を十分に持っていたという事です。傾向変わったと文句を言っている人がその人たちに勝てると思いますか?私は勝てないと思います。傾向変えられても対応できるかの力は模試で測られています。それも含めても偏差値です。「判定がC判定も出ていないけど過去問をしっかりやった結果受かりました」なんて話はほとんど聞きません。基本的には判定通りになる気がします。
そういった現状なのでまずは何処何処を受けるからその対策をするのではなくて、色々な問題に対して応用できる基礎力が大切です。例えば、古文漢文と英語であれば文法と単語です。これらは文法がきちんと出来ていないとどうしようもありません。逆に言えば、文法と単語をきちんと覚えていれば文章を変えられても同じように訳したりすることが出来ますよね。なので、まずは文法と単語をしっかりとやってください。記述でまとめる力は応用ということになると思います。それもまずは訳したり出来ないと話になりませんよね。
数学であればこれまでに習った数学ⅠAⅡBまでの公式をしっかりと使いこなせるかどうかです。例えば、三角関数の変形はしっかりと出来ますか?微分の計算はきちんと出来ますか?それらの中で出来ない分野があればそこの復習をしっかりとしましょう。